河北新報特集紙面2024
2025年3月30日 河北新報掲載
震災伝承新聞完成レポート②中学生がつなぐ記憶と教訓
取材で得た学びの成果を共有
2月27日、聖ウルスラ学院英智小・中で震災伝承新聞の完成報告会が行われ、中学生記者が5年生から9年生までの275人と取材成果を共有しました。全員で震災犠牲者に祈りを捧げた後、取材に参加した生徒が南三陸町で得た気づきを当日の画像を交えながら述べました。
全てのライフラインが寸断した過酷な状況下、600人の避難者ほか現場対応の警察・医療従事者ら400人も受け入れ、被災後の前線基地の役割を果たした「南三陸ホテル観洋」の女将、阿部憲子さんの講話と副支配人の阿部裕樹さんの案内で高野会館など町内を巡った「語り部バス」で被災の現場に身を置いた得がたい経験を紹介。「戸倉SeaBoys」メンバーの漁船で見学した日本初の国際認証制度を獲得したカキ養殖施設では、どん底にあっても前を向き、力を合わせて努力する大切さを学んだことを報告。大災害に遭遇した時、判断を迫られる命を守る行動について語り合うラーニングプログラムに参加した「南三陸311メモリアル」で、防災意識を高め合うことができた成果を披露しました。
発表を聞いた生徒からは、自然災害が多い昨今、備えの大切さを改めて感じたことが述べられました。

講堂に集まった5〜9年生の前で中学生記者が発表

発表会参加者
三塚 勇輝さん(7年)
災害の被害を完全に無くすことはできませんが、例えば、現地を訪れたり、お話を聞いたりすることで災害のおそろしさを学び、地震や津波への備えをするなど、自分でできることはたくさんあると思いました。
今回参加した中学生記者全員の「声」

-
岡部 佐和子さん(9年)
未来目指す姿勢に感銘 - 震災を経験した方の体験談は重みがあり、写真や映像では分からない部分を知ることができました。語り部クルーズの横山純子さんの「明日はいつも通りには来ないかもしれない」という言葉は、自分の普段の行動を見直すきっかけになりました。今できることを先延ばしにすると、一生後悔するかもしれません。今回の取材の体験を、ずっと今後に生かしていくつもりです。
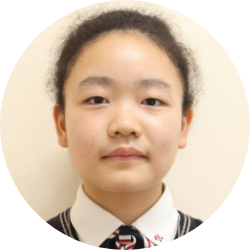
-
木村 咲彩さん(8年)
自分にできること探る - 特に印象に残ったのは「私たちにできることを考えるのが大事」という南三陸ホテル観洋の女将、阿部憲子さんの言葉です。新聞などで、被災地への多額の寄付や現地での支援活動について読んでも、私にはこうした活動は難しいと考えていました。しかし、この言葉を聞いて「少額でも寄付などで貢献ができる」と自分にできることを考え直しました。取材に参加して、後世の人たちに震災について考えてもらえる活動がしたいと思うようにもなりました。

-
佐藤 えれなさん(9年)
迫る津波の恐怖追体験 - 語り部バスの体験が強く印象に残っています。跡形もない戸倉小や、旧戸倉中で津波到達時刻のままの時計を見て、私たちと同世代の人たちが感じた津波の恐怖を追体験しました。シャンデリアの破片やはがれ落ちた壁紙など、あの日のまま残されている高野会館を案内いただいた阿部裕樹さんのお話から、懸命に避難する人々の当時の様子が目に浮かびました。自然の営みとともに生きていく私たちは、防災に努めなければならないと強く感じています。

-
佐藤 智埜さん(8年)
南三陸の苦難忘れない - 震災を風化させないよう後世に伝えてゆく必要があると強く思いました。多くの人や物が被害を受け、葛藤や苦難を乗り越えて今の南三陸の姿になったと取材で実感しました。震災で町は831人が犠牲になり、6割近くの建物が全壊したそうです。復興までの間にそれぞれの場所でさまざまな人たちの努力によって今の地域があります。あの日、震災によって被災された方々の思いを無に帰さないために、自分よりも下の世代に伝えていきたいと思います。
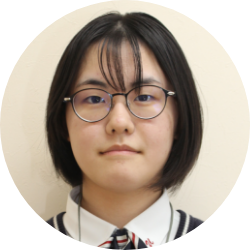
-
嶋 悠花さん(8年)
減災へ関心持ち続ける - 皆さんのお話から、悲惨な出来事を伝えることへの葛藤や震災で負った心の傷が伝わってきて、語り部活動をすることの大変さを感じました。一番印象に残ったのは「東日本大震災は1000年に1度の災害ではなく、1000年に1度の教訓」という言葉です。私は震災の年に生まれ、震災の記憶はまったくありません。でも、そこで「私には関係ない」と言って避けるのではなく、「貴重な教訓だ」と関心を持つことが減災につながるのではないかと思いました。

-
鈴木 悠真さん(9年)
記憶伝承 私たちが担う - 被災した皆さんの当時の思いや決意に強い印象を受けました。ただ悲しい、悔しいだけでなく、その体験を繰り返さないよう、後世に残していくという強い熱意でした。今まで震災のことをある程度はわかっているつもりでしたが、取材を通してほんのわずかだったと気付かされました。私は震災当時幼く、記憶がほとんどありません。この先に生まれる子どもはその知識がさらに薄れるのでしょう。だからこそ、私たちが思いを受け継ぎ、伝えていくべきだと思いました。
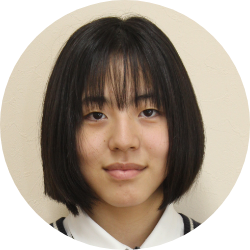
-
高橋 芽衣子さん(8年)
水産復活へ熱意感じた - 震災のことはテレビや本、ウェブなどの情報でしか知りませんでした。実際に南三陸町を訪れて被災者のお話を聞くと、震災時の雰囲気が感じ取れると同時に、復興への強い意志が伝わってきました。戸倉Sea Boysの皆さんは、水産業復活に取り組み、震災前よりも良い環境で仕事をしていることを、とても生き生きとした表情でお話していました。今回のプロジェクトを通して、南三陸町は着実に復興を遂げつつあることを体感することができました。
「震災伝承新聞」は、宮城県内184の中学校へ配布したほか、石川県輪島市立門前中、愛媛県今治市立近見中、兵庫県西宮市立浜脇中などで教材として活用されました。各地の震災伝承施設、仙台市図書館、そなエリア東京、宮城県大阪事務所などでも配布しています。
[お問い合わせ]
今できることプロジェクト事務局(河北新報社営業部)
tel 022-211-1318(平日10:00〜17:00)

中学生記者
鈴木 悠真さん(9年)
被災地で生まれ育った一人の若者として、震災の話を聞き、それを同世代に語り継ぐことができたことを誇りに思います。この先も決して風化させず、震災の記憶を胸に刻み、次世代への教訓として守り抜きたいと思います。